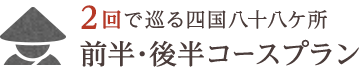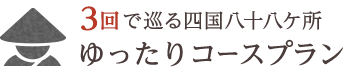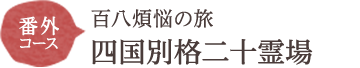こんにちは!乙ママです!!
この週末からお盆休みに入る方も多いのではないでしょうか。
高松ではこの時期になると、お墓に白い何かがたくさん飾ってある風景がよく見られます。
私は実家が岡山なのですが、高松に住むようになってこのお盆の季節になるとみたことのないものを見てびっくりしました。

この白い飾りは「さぬき盆灯篭(ぼんとうろう)」というそうです。
このさぬき盆灯篭について岩佐佛喜堂の代表である岩佐さんからお話を伺いました。

この白い灯篭を飾る風習があるのは主に西讃から坂出、高松。
古くからの風習として続いており、宗派は関係なく行われます。
お盆の時期にお墓に飾る盆灯篭は「お墓灯篭」ともいい、お墓参りの時にお線香やろうとくと一緒にお供えします。
真っ白なものもあれば、色のついた飾りがついたものまであります。
こちらは水色バージョンです。他にもいろんな色があります。

お墓に供える灯篭の他に、お仏壇にお供えする灯篭もあります。
こちらは「お仏壇灯篭」といいまして、亡くなられてから3年の間、お盆にお仏壇の前につるすそうです。

こちらの灯篭には白、銀、金と3色あり、
白が1年目、銀が2年目、金が3年目にお供えするそうです。

また、昔は8月いっぱい飾り終えた盆灯篭を海に流していたそうです(今は海に流すのは禁止されています)。
それにしてもこの灯篭、とても美しいですよね!細工の細かさにはびっくりします。

この蓮の花の誂え、本当に美しいですね。

いわゆる工芸品として目にする機会はないのですが(基本的にお盆が終われば破棄するからでしょうが)、
伝統工芸に値するものだと思いました。
岩佐さんも「このような風習がいつまでも残っていてほしいと思っています」とおっしゃってました。
さぬき盆灯篭だけでなく、地域独特のお盆の風習を知るのは味わい深いです。
お盆でお墓参りに行かれる際や、旅先でお寺などに行かれる際に、
ちょっと気に留めて見回してみると、意外と面白い発見があるかもしれません。
岩佐佛喜堂さんでは、お遍路の88箇所を始めとしたそれぞれのお寺をテーマに、お香を作っているそうです。
行ったことのあるお寺がどのような香りか、気になりますね!

お話いただきました岩佐さん、撮影にご協力くださいましたスタッフの皆様、ありがとうございました。