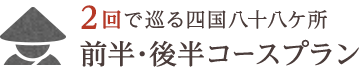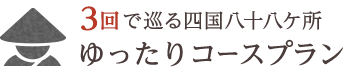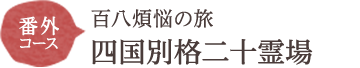寒い寒いと口癖になってしまうほどに温度が下がり、正に冬本番といった季節になってまいりました。
こんにちは。ハチハチ編集部のまさです。
「霊場巡りと言えば四国八十八ヶ所!」
そんなイメージが湧いてくる四国八十八ヶ所霊場巡りですが、
四国八十八ヶ所霊場巡りに感銘を受けて、開創された霊場が全国各地にあるようです。
今回は全国各地にある霊場巡りについて紹介したいと思います。
全国各地に点在する八十八ヶ所
香川県 小豆島八十八ヶ所
四国の北方、瀬戸内海に浮かぶ島々の中で2番目に大きい島、小豆島の霊場巡りです。
この霊場は、弘法大師空海が香川県と京都を往復する際、小豆島に度々立ち寄り修行を行ったといわれていて、弘法大師が開創した四国八十八ヶ所に倣って1686年に小豆島の僧侶たちによって開創されたのが由来と言われています。
この霊場巡りは、篠栗(ささぐり)四国八十八ヶ所、知多四国八十八ヶ所と共に日本三大新四国霊場に数えられることもあります。
福岡県 篠栗四国八十八ヶ所
この霊場巡りは、慈忍(じにん)という尼僧(女性の僧侶)が1835年ごろ、篠栗に訪れた事が開創されるきっかけとなりました。
四国八十八ヶ所霊場巡りの帰り道、篠栗に寄った慈忍は弘法大師も訪れたとされる村に立ち寄りました。
そこで彼女が見たものは村人たちの困窮。
彼女は弘法大師の名のもとに祈願を続け、やがて村に安寧をもたらしたそうです。
活気が戻った村人たちに四国八十八ヶ所霊場巡りを模した霊場の造成を提案、紆余曲折ありながらも1854年にすべてが完成、開創されました。
第1番札所の南蔵院には、世界最大の銅でできた仏像、釈迦涅槃像があります。
愛知県 知多四国八十八ヶ所

この霊場巡りは、弘法大師が東国巡錫の途中に知多半島を訪れ、上陸した際に見えた知多の風景が四国にとても似ていたことから、四国を懐かしみ「西浦や 東浦あり 日間賀島 篠島かけて 四国なるらん」という和歌を詠い知多に残しました。
その後、知多の住職の夢の中で弘法大師からのお告げがあり、お告げを成就するために二人の同志を集めました。
そして、三度の四国八十八ヶ所霊場巡りの参拝を経て、1809年に知多四国霊場を開創されました。
なぜ「四国」の名前が?
なぜ四国ではない場所に「四国」という名前が使われているのか、それには理由があります。
これらの霊場巡りは、すべて四国八十八ヶ所霊場巡りを模して作られたものです。
四国以外の場所でも四国霊場ほどのご利益がいただけるように願い開創され、「四国」の名前をつけられました。
また、これらの霊場巡りは「地四国」と呼ばれ、全国に点在しています。
島で行われる霊場巡りは島四国とも呼ばれるようです。
今でもにぎわっている遍路のあり方は、弘法大師の影響力の大きさを窺い知ることができます。
多くの参拝者がいて、歴史の波に流されることなく続いていく霊場巡り。
その体験は、訪れた場所でさまざまな出会い、歴史を学ぶことができます。
――――――――――
さまざまな場所にある霊場巡り、どの場所も人の願いが込められていて、どれも人の温かみを感じられますね。
ハチハチ編集部 | まさ